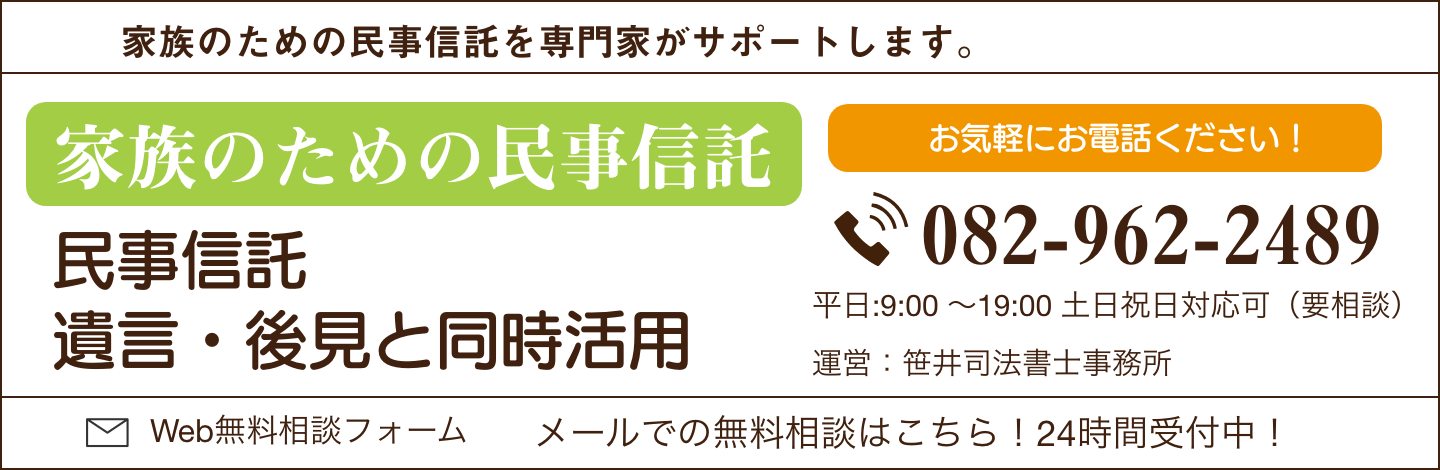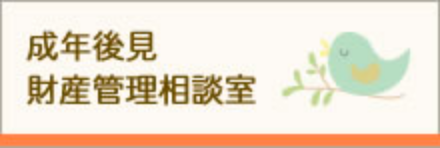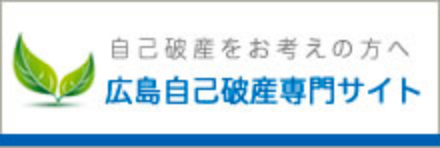その他の方法との比較
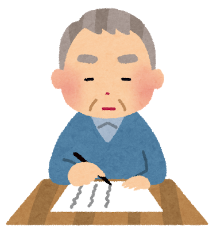
本人が死亡した際に財産を誰かに遺す方法として、以前から「遺言」があります。
遺言を作ることで、自分の財産の行方を決めておくことができ、法定の相続分割合以外の割合や相続人以外にお世話になった人に対して財産を渡すことも可能です。
ただし遺言にもいくつかのメリット・デメリットがあります。
遺言のメリット
- 本人の思う通りの遺産の配分ができる。
- 法定相続人以外にも遺産を相続させることができる。
- 相続人が遺産分割方法について悩まなくて済む。
遺言のデメリット
- 死亡まで効力が生じない。
- 相続人全員が不満であれば遺言を実行せずに撤回できる。
- いつでも書き換えることが可能
- 遺言書を関係者が破棄・隠匿する恐れがある。
民事信託の制度を利用することで、これらの遺言の弱点をカバーすることができ、遺言では達成できなかったことも可能になります。
民事信託で財産を承継するには「遺言信託」と「遺言代用信託」の方法があります。
いずれも、自身の判断能力が低下する前に利用することになります。
「遺言信託」と「遺言代用信託」は全く別物です。
「遺言代用信託」は民事信託の仕組みを使うことで、「遺言」の「代用」ができる「信託」契約のことです。真の所有者である「受益者」の死亡により「受益権」を受け取る人を指定することで、遺言における「どの財産」を「誰に」相続させるか、という機能と同様の効果を得られます。
また「遺言信託」にも、金融機関の商品としての遺言信託と、法律用語としての遺言信託があり、似て非なるものなので注意が必要です。
金融機関の商品としての遺言信託とは、金融機関が遺言の相談から作成、保管まで行い、死亡時には遺言執行者となり、死亡した本人の想いを実現する金融商品になります。
メリットとしては金融機関が身近な存在であることですが、デメリットとしては費用が高いこと(最低報酬は少ないところでも100万円)、
相続人間で争いがあると引き受けてもらえないこと等が挙げられます。
法的な意味での遺言信託とは、遺言によって信託を設定する行為のことです。
| 遺言 | 遺言信託 | 遺言代用信託 | |
|---|---|---|---|
| 効力の発生時期 | 遺言の作成者の死後に効力が発生。 | 遺言の作成者の死後に効力が発生。 | 信託契約に定めた時期から効力が発生。 |
| 財産の移転方法 | 遺言の作成者の死後、相続人または遺言執行者によって、相続人や受遺者に財産が引き渡される。 | 遺言の作成者の死後、相続人または遺言執行者によって、相続人や受遺者に財産が引き渡される。 | 委託者の生前に、信託契約で定めた内容に従って受託者に財産が引き渡される。 |
| 家庭裁判所の手続き | 公正証書以外の「遺言」の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要になる。 | 公正証書以外の「遺言」の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要になる。 | 不要 |
| 遺言および信託の変更 | 作成者は遺言をいつでも変更できる | 作成者は信託内容をいつでも変更できる | 信託内容は委託者及び受託者の合意によって変更できる。 |
| 遺言および信託の撤回 | 作成者は遺言をいつでも撤回できる | 作成者は信託内容をいつでも撤回できる | 委託者及び受託者の合意によって信託を終了することができる。 |
| 財産の管理・運用・処分の範囲 | 生前の財産管理・運用・処分については効力がない | 生前の財産管理・運用・処分については効力がない | 受託者の権限の範囲内であれば、信託目的に沿った自由な運用・処分が可能。 認知症になった場合の財産管理方法を決めておくことも可能 |
民事信託のポイント (遺言制度と比較して)
- 民事信託は契約なので、一方的に破棄・撤回できない
- 第2第3の承継者を定めることができる
- 節税効果はない
- 遺産分割の指定も可能
- 関係者の破棄隠匿はできない
- 所有権は受託者へ移転する
- 遺言は死んでからしか効力がないが、民事信託は生きているうちから効力を生ずる
「遺言代用信託」であれば認知症になった場合の財産管理方法を決めておくことも可能であるため、受託者の権限によって入所費用などを財産からまかなうこともできます。当事務所では依頼される方の状況を伺いながら、ご本人や家族の方にとって最適なスキーム(方法)をご提案させていただきます。
 電話する
電話する アクセス
アクセス メニュー
メニュー
 ホーム
ホーム 民事信託について
民事信託について 他の方法
他の方法 手続きの流れ
手続きの流れ 事務所紹介
事務所紹介 お問い合わせ
お問い合わせ